- まわりにうつることもある急性腸炎
- 急性腸炎の原因
- 急性腸炎の症状
- 急性腸炎の検査
- 急性腸炎の治療
- 学校や仕事は休んだ方がいい?急性腸炎の潜伏期間について
- 夏場に注意!刺身などからうつる細菌性腸炎「腸炎ビブリオ」
まわりにうつることもある急性腸炎
 急性腸炎とは、腸の粘膜に急性の炎症が起こる病気です。
急性腸炎とは、腸の粘膜に急性の炎症が起こる病気です。
吐き気や嘔吐、腹痛、下痢、発熱などの症状を伴います。原因はいくつかありますが、細菌・ウイルスの感染を原因とする場合には、まわりの人へとうつしてしまうことがあります。
急性腸炎の原因
急性腸炎の原因は、以下のように分けられます。
感染性胃腸炎
ウイルスや細菌などの感染を原因とするタイプです。
ウイルス性腸炎
ノロウイルス、ロタウイルス、アデノウイルスなどが原因となります。
感染している人の吐物・唾液・便などに含まれるウイルスが飛沫感染と接触感染し、まわりの人へとうつります。
細菌性腸炎
カンピロバクター菌、サルモネラ属菌、腸管出血性大腸菌(O157)などが原因となります。
細菌に汚染された水・食品の摂取、細菌が付着した手指の口への接触などにより感染します。
非感染性胃腸炎
食物アレルギー、暴飲暴食、冷たいものの摂り過ぎなどが主な原因となります。
急性腸炎の症状
- 吐き気、嘔吐
- 腹痛
- 食欲不振
- 下痢
- 血便
- 発熱
嘔吐、下痢、発熱といった症状による脱水にも注意しなければなりません。
急性腸炎の検査
問診では、症状やその経過、過去1~2週間程度の食事内容、ご家庭や職場・学校などでの感染症の流行状況、最近の渡航歴、抗菌薬の使用歴などについてお尋ねします。
その上で、以下のような検査を行います。
血液検査
症状が強く現れている場合には、炎症・脱水の程度を調べるために血液検査を行います。
便培養検査
細菌感染を疑う場合には便や腸液の培養検査を、ウイルス感染を疑う場合には便・腸液を用いた抗原検査を、それぞれ行います。
ノロウイルス抗原検査は、3歳未満または65歳以上の方のみ保険適用となります。
急性腸炎の治療
診断後は、主に以下のような治療を行います。
食事療法・水分補給
胃腸に負担をかけない、消化の良いものを食べます。また病状によっては、一定期間の絶食を行うこともあります。
いずれの場合も、脱水症状を防ぐため、小まめに水分補給を行ってください。電解質・糖がバランス良く含まれる経口補水液がおすすめです。水分を摂れない場合、重度の脱水を起こしている場合には、点滴が必要になります。
薬物療法
症状に応じた対症療法を行うのが基本です。
整腸剤、解熱剤、吐き気止めなどを使用します。また細菌感染が強く疑われる場合には、抗菌薬を使用することもあります。
下痢止めを使用すると、病原体が腸に残ってしまうため、基本的には使用しません。
学校や仕事は休んだ方がいい?急性腸炎の潜伏期間について
 ウイルス性の場合は1~3日程度、細菌性の場合は1~7日程度の潜伏期間があります。ただ、O-157等の特定の病原体の感染を原因とする場合を除き、出席停止期間は決められていません。
ウイルス性の場合は1~3日程度、細菌性の場合は1~7日程度の潜伏期間があります。ただ、O-157等の特定の病原体の感染を原因とする場合を除き、出席停止期間は決められていません。
基本的には、症状が落ち着いて元気になれば、登園・登校、出社は可能です。ただし、自治体や幼稚園・学校・職場などによっては独自のルールがあるので、確認が必要です。
夏場に注意!刺身などからうつる細菌性腸炎「腸炎ビブリオ」
 腸炎ビブリオは、海水に生息する細菌で、刺身や寿司、魚介類などの加熱が不十分な海産物を食べることで感染する食中毒の原因菌です。特に夏場など、気温が高くなる時期に増殖しやすく、注意が必要です。
腸炎ビブリオは、海水に生息する細菌で、刺身や寿司、魚介類などの加熱が不十分な海産物を食べることで感染する食中毒の原因菌です。特に夏場など、気温が高くなる時期に増殖しやすく、注意が必要です。
感染経路と原因食品
- 生の魚介類(刺身、寿司、貝類など)
- 魚介類を調理したまな板や包丁などを介しての二次汚染
魚介類を常温で放置したり、調理器具の洗浄が不十分だったりすると、菌が急速に増殖し感染リスクが高まります。
潜伏期間と症状
- 潜伏期間:約8〜24時間
- 主な症状:激しい腹痛、下痢、吐き気、発熱、血便など
腸炎ビブリオは、感染後に突然強い腹痛と水様性の下痢を引き起こすのが特徴で、症状が激しいことが多いため早めの受診が推奨されます。
感染経路と原因食品
- 魚介類は新鮮なものを選び、できるだけ加熱調理する
- 生食用の魚介類は10℃以下で保存する
- 調理器具や手指は魚介類の調理後に十分に洗浄・消毒する
感染経路と原因食品
腸炎ビブリオは自然に回復することが多いですが、脱水予防のための水分補給や整腸剤などによる対症療法が中心となります。症状が重い場合は抗菌薬を使用することもあります。





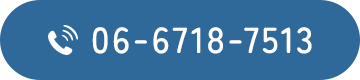



 症状が長引いている場合には、潰瘍性大腸炎、クローン病などとの鑑別のため、大腸カメラ検査を行います。
症状が長引いている場合には、潰瘍性大腸炎、クローン病などとの鑑別のため、大腸カメラ検査を行います。