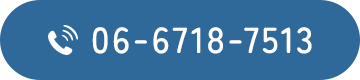胃の不調、それは「胃炎」かもしれません

- なんだか胃が重たい
- 食欲が出ない
- ムカムカして気持ちが悪い
そんな胃の不調、放っていませんか?
これらの症状は、胃の粘膜に炎症が起きている『胃炎』のサインかもしれません。
胃炎には、大きく分けて「急に症状が出る急性胃炎」と「長期間にわたって胃に炎症が続く慢性胃炎(萎縮性胃炎)」の2種類があります。
それぞれ原因や治療法が異なるため、正確な診断と適切な対応が重要です。
このページでは、急性と慢性の胃炎の違いや、検査・治療の内容をわかりやすくご紹介します。
急性胃炎とは
急性胃炎とは、胃粘膜で生じる急性の炎症です。
原因
暴飲暴食、刺激物の摂り過ぎ、ウイルス・細菌感染、非ステロイド系抗炎症薬・抗菌薬の内服などが挙げられます。
症状
主に、以下のような症状が見られます。
- 胃痛、胃の不快感
- 吐き気、嘔吐
- 発熱
- 腹痛
- 下痢
- 黒色便(タール便)、吐血
- 貧血
検査
問診では、症状、直近1~2週間の食事内容、家庭・学校・職場での感染症の流行状況、最近の渡航歴などについてお伺いします。
その上で、血液検査、便・腸液の培養検査、胃カメラ検査などを必要に応じて行い、診断します。
治療
多くの場合、原因を取り除き、絶食し胃を休ませることで改善します。必要に応じて、胃酸の分泌を抑える薬、胃粘膜を保護する薬、解熱剤、整腸剤などを処方します。また細菌性の急性胃炎が疑われる場合には、抗菌薬を使用することもあります。
安静中も、脱水を防ぐため小まめに水分補給を行います。電解質・糖がバランスよく含まれる経口補水液がおすすめです。脱水を起こした場合には、点滴による輸液が必要になります。
慢性胃炎(萎縮性胃炎)とは
慢性胃炎とは、胃の炎症が慢性化している状態です。急性胃炎と異なり、慢性炎症が長期にわたると、胃の粘膜細胞にDNA損傷や異常な細胞増殖が起きやすくなり、がん化(胃がん)のリスクが高まります。
原因
全体の8割以上が、ピロリ菌感染を原因として発症すると言われています。特に、萎縮性胃炎・鳥肌胃炎といったピロリ菌感染を原因とする胃炎は、胃がんとの強い関連性が指摘されており、注意が必要です。
症状
慢性胃炎は多くの場合、無症状です。胃カメラ検査を受けて初めて慢性胃炎を指摘されるケースも少なくありません。
ただその中でも、以下のような症状が見られることがあります。
- 胃もたれ
- 吐き気
- 消化不良
検査
問診では、症状、最近の食生活、服用中のお薬などについてお伺いします。
その上で、胃カメラ検査を行い、診断します。胃粘膜が薄くなる萎縮性胃炎に進行している場合には、胃がんのリスクが高まります。胃カメラ検査の際には、組織を採取してピロリ菌を行うこともできます。
治療
生活習慣の改善
暴飲暴食、刺激物・アルコール・カフェインの摂り過ぎを控え、規則正しい食生活を送ります。
喫煙、ストレスなど、胃炎の悪化因子を取り除くこと、十分な睡眠をとること、軽く汗をかく30分程度の運動を週2回を目安に継続することなども大切です。
薬物療法
必要に応じて、慢性胃炎に伴う胃もたれ、吐き気、消化不良などの症状を改善するためのお薬を処方します。
ピロリ菌の除菌治療
ピロリ菌検査で陽性だった場合には、胃酸の分泌する薬、抗菌薬を用いたピロリ菌除菌を行います。
ピロリ菌は慢性胃炎・萎縮性胃炎・胃がん、また胃・十二指腸潰瘍の原因となる細菌です。慢性胃炎の再発予防、またその他の病気の予防という意味でも、除菌治療は重要な治療となります。
萎縮性胃炎とピロリ菌の関係
 萎縮性胃炎の主な原因のひとつが、「ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)」の感染です。
萎縮性胃炎の主な原因のひとつが、「ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)」の感染です。
ピロリ菌は胃の中にすみついて、長い年月をかけて胃の粘膜に炎症を引き起こします。
ピロリ菌がいると、胃の粘膜がダメージを受け続ける
ピロリ菌は、胃酸という強い酸の中でも生きられる特殊な細菌です。
感染していると、胃の粘膜に慢性的な炎症を起こし、やがて粘膜がうすく弱くなっていきます。
この状態が進行すると「萎縮性胃炎」と呼ばれ、胃の働きが低下してしまいます。
萎縮性胃炎が進むと、胃がんのリスクも上がる
萎縮性胃炎が長く続くと、胃の粘膜がさらにダメージを受け、胃がんの発生リスクが高まることがわかっています。そのため、ピロリ菌の感染が確認された場合は、早めの除菌治療がとても重要です。
ピロリ菌の検査と除菌は、保険で行えます
当院では、胃カメラ検査で萎縮性胃炎が疑われた場合、ピロリ菌の検査を保険適用で行うことができます。
ピロリ菌が陽性であれば、内服薬による除菌治療を行い、胃の粘膜を健康に保つことが将来の胃がん予防にもつながります。
急性胃炎と胃腸炎の違いは?
 急性胃炎では、胃の粘膜で急性の炎症が起こり、突然、胃痛や吐き気・嘔吐といった症状が現れます。原因としては、暴飲暴食、刺激物の摂り過ぎ、ウイルス・細菌感染、非ステロイド系抗炎症薬・抗菌薬の内服などが挙げられます。
急性胃炎では、胃の粘膜で急性の炎症が起こり、突然、胃痛や吐き気・嘔吐といった症状が現れます。原因としては、暴飲暴食、刺激物の摂り過ぎ、ウイルス・細菌感染、非ステロイド系抗炎症薬・抗菌薬の内服などが挙げられます。
対する胃腸炎では、病名の通り、胃と腸で炎症が見られます。ウイルス・細菌感染が原因になることが多く、吐き気・嘔吐、発熱、腹痛、下痢といった、胃・腸の症状が現れます。
症状が胃に留まる場合には急性胃炎を、発熱や下痢がある場合には胃腸炎を疑うのが一般的ですが、正確な診断のためにはやはり医療機関の受診が必要になります。
胃炎は自然に治る?放置するリスク
急性胃炎の場合には、絶食によって胃を休ませることで、自然に治ることが多くなります。ただその絶食期間も、小まめに水分を摂取することが大切です。
一方の慢性胃炎は、多くがピロリ菌感染を原因とします。ピロリ菌は、除菌治療をしない限り感染を持続させます。そのため、胃を休ませて多少、症状が軽くなっても、根本的な原因が取り除けていないことが多く、自然治癒は期待できません。また放置すると萎縮性胃炎へと進行し、胃がんの原因になることもあります。
ただ、急性胃炎だから必ず自然治癒するというわけではありません。また、急性胃炎だと思っていたら他の病気だったということも十分に考えられるため、やはり医療機関を受診するのが安心です。