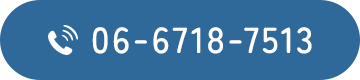- おならが増えた・ガスが溜まって苦しい…
- おならがよく出る・ガスが増える原因
- おならが多い・ガスが溜まりやすい体質はある?
- ストレスでおならが臭くなる理由
- おならが止まらない時に考えられる病気とは
- おならを減らす方法
- ガスが溜まってお腹が張る・痛いときの対処法
- 「おならが止まらない・ガスが苦しい」とお悩みの方へ
おならが増えた・ガスが溜まって苦しい…
 おならが増えた・ガスが溜まって苦しいといった症状は、一過性のものであれば、それほど心配はいりません。多くの場合、肉類やイモ類・豆類の食べ過ぎなどが原因となっており、食生活を改善することで、比較的短期間で治まります。
おならが増えた・ガスが溜まって苦しいといった症状は、一過性のものであれば、それほど心配はいりません。多くの場合、肉類やイモ類・豆類の食べ過ぎなどが原因となっており、食生活を改善することで、比較的短期間で治まります。
ただ、中には過敏性腸症候群などの病気を原因として上記のような症状が続く場合もあります。
おならが増えた・ガスが溜まって苦しいという症状が長引く時、食生活を改善しても良くならない時には、一度当院にご相談ください。
おならがよく出る・ガスが増える原因
肉類の摂り過ぎ
肉類を摂り過ぎると、腸内でタンパク質を分解する際に、多量のガスが発生します。おならが増えるだけでなく、においもきつくなります。
イモ類・豆類の摂り過ぎ
イモ類や豆類など、食物繊維の豊富な食品を摂り過ぎると、大腸で多量のガスが発生します。
便秘
腸内に便が長く留まると、ガスも発生しやすくなります。
運動不足
運動不足によって胃腸の動きが鈍くなり、便秘、およびおならの増加が見られることがあります。
ストレス
ストレスによって自律神経のバランスが乱れ、胃腸の働きが低下することで、おならが増えることがあります。
疾患
過敏性腸症候群、大腸がんなどの疾患を原因として、おならが増えることがあると言われています。
おならが多い・ガスが溜まりやすい体質はある?
「おならが出やすい」「お腹にガスが溜まりやすい」といった体質には、いくつかの要因が関係しています。遺伝的な体質だけでなく、生活習慣や食習慣、腸内環境などが複雑に絡み合っている場合が多くみられます。
腸内環境の違い
腸内細菌のバランスは人によって異なります。ガスを発生しやすい腸内細菌が多い場合、同じものを食べても他の人よりガスが発生しやすくなります。
食べ物の消化吸収の違い
豆類やキャベツ、ブロッコリーなどの食物繊維が豊富な食品は、消化の過程でガスが発生しやすいとされています。これらを分解する酵素の働きが弱い方は、ガスが溜まりやすい体質と感じることがあります。
空気を飲み込みやすい癖(空気嚥下症)
食事中や会話中に無意識に多くの空気を飲み込むクセのある方(早食い、ガムの咀嚼、炭酸飲料の摂取など)は、腸内に空気が溜まりやすくなり、おならや腹部膨満の原因になります。
過敏性腸症候群(IBS)などの影響
体質とは異なりますが、腸が過敏に反応しやすい「過敏性腸症候群(IBS)」では、少量のガスでもお腹の張りを強く感じたり、おならが頻繁に出やすいことがあります。
ストレスでおならが臭くなる理由
 ストレスによる自律神経の乱れは、先述の通り胃腸の働きを低下させ、おならを増加させる原因になることがあります。
ストレスによる自律神経の乱れは、先述の通り胃腸の働きを低下させ、おならを増加させる原因になることがあります。
加えて、ストレスを抱えている状態が食べ過ぎなどの食生活の乱れを招きやすいこと、ストレスによる免疫力の低下に伴い腸内細菌叢のバランスが崩れることから、おならが臭くなりがちです。
おならが止まらない時に考えられる病気とは
過敏性腸症候群
腹痛・下痢・便秘といった症状が繰り返されます。症状の現れ方により、下痢型・便秘型・交代型・分類不能型に分けられます。うち、便秘型や分類不能型では、おならが増える等の症状が見られることがあります。
小腸内細菌増殖症(SIBO)
小腸の細菌が異常増殖する病気です。これらの細菌によって大量のガスが発生することで、おならが増えます。その他、腹部膨満感、腹痛、ゲップ、便秘、下痢などの症状も見られます。
腸閉塞
腹部手術、大腸がん、ひどい便秘などにより、腸内で便が詰まってしまった状態です。お腹の張りやおならの増加、腹痛、吐き気・嘔吐、発熱などの症状を伴います。緊急手術が必要になることもあるため、すぐに受診してください。
機能性ディスペプシア
胃カメラ検査などで器質的な異常が認められないのに、慢性的な胃の不快感が続く病気です。胃痛や胃もたれ、腹部膨満感、腹痛などの症状が見られます。発症には、ストレスが大きく関与しているものと思われます。
呑気症
早食い、一気飲み、口呼吸などの癖・習慣、あるいはストレスなどにより、空気をたくさん飲み込んでしまうことを指します。ゲップ、おならが増えます。
胆汁性下痢
胆汁酸が小腸でうまく吸収されず、大腸に過剰に流れ込むことで下痢を引き起こす病気です。腸内環境の乱れや蠕動運動の異常により、ガスが発生しやすくなり、おならが増えることがあります。
おならを減らす方法
食事
よく噛んでゆっくり食べる
よく噛むことは、食べ物の胃腸での消化を助けます。また、ゆっくり食べることは、空気の飲み込みを予防します。ジュースやドリンクなどの一気飲みをしないこと、炭酸飲料を控えることなども有効です。
栄養バランスの良い食事を摂る
栄養バランスの良い食事を摂ることは、腸内細菌叢のバランスを整えるのに有効です。肉類・イモ類・豆類は特におならの原因となりやすいため、完全に避ける必要はありませんが、摂り過ぎないようにしましょう。
発酵食品を意識して摂る
ヨーグルト、キムチ、納豆などの発酵食品は、腸内環境を整える善玉菌を多く含みます。腸内細菌叢のバランスを整え、ガスを減らす効果が期待できます。
水分・食物繊維を意識して摂る
便秘がある場合には、水分・食物繊維を意識して摂取しましょう。水溶性食物繊維・不溶性食物繊維をバランスよく摂ることが大切です。摂り過ぎは逆におならが増える原因になるため、ほどほどにしてください。
その他
人工甘味料、乳製品などは、ガスを発生させる原因になると言われています。摂り過ぎないようにしましょう。
運動
適度な運動を継続的に行う
適度な運動は、胃腸への良い刺激となり、胃腸の働きを正常化させます。ウォーキング、軽いジョギング、ストレッチ、ヨガなど、1日30分程度の運動を継続しましょう。
生活習慣
ストレスを溜めない
ストレスは自律神経のバランスを乱し、胃腸の働きを悪くさせる原因となります。ご自身に合った方法で、小まめにストレスを解消しましょう。
規則正しい生活を送る・十分な睡眠をとる
不規則な生活リズム、睡眠不足は、どちらも自律神経のバランスを乱し、胃腸の働きを低下させるおそれがあります。
姿勢に気をつける
猫背、前屈みの姿勢は、腹圧を上昇させ、消化を妨げたり、おならを増やすことがあります。デスクワークの人は、特に姿勢が悪くならないように気をつけましょう。
ガスが溜まってお腹が張る・痛いときの対処法
お腹にガスが溜まって張ったり、痛みを感じるときには、無理に我慢せず、体に負担をかけないような工夫が大切です。以下のような点に注意しましょう。
楽な姿勢をとる
ガスが動きやすいように、少し体を丸めて横向きに寝たり、ひざを抱える姿勢をとると、腸がリラックスしてガスが抜けやすくなることがあります。特に「左側を下にして横になる姿勢」は効果的です。
軽い運動で腸を刺激
ガスが溜まって苦しいときは、無理のない範囲で軽く体を動かす(散歩や足踏みなど)と、腸の動きが活発になりガスが排出されやすくなります。長時間座りっぱなしや寝たきりは逆効果になることもあるので注意が必要です。
お腹を温める
腹部をカイロや温タオルで温めることで、腸の動きが良くなり、ガスの排出が促される場合があります。冷えが原因で腸の動きが低下していると感じるときには特におすすめです。
痛みが強い・繰り返す場合は受診を
ガスによる膨満感や痛みは一時的なことが多いですが、以下のような場合は他の病気が隠れている可能性もあります。自己判断せず、医療機関にご相談ください。
- 少量の食事でもすぐにお腹が張る
- お腹の痛みが繰り返す、または強い
- 吐き気・嘔吐・発熱などの症状を伴う
- 排便異常(便秘・下痢など)を繰り返している
「おならが止まらない・ガスが苦しい」とお悩みの方へ
 おならの回数が多い、ガスが溜まってお腹が苦しい、といった症状は、日常生活の質を大きく下げるものです。恥ずかしさから相談しにくいと感じる方もいらっしゃいますが、実は多くの方が同じようなお悩みを抱えています。
おならの回数が多い、ガスが溜まってお腹が苦しい、といった症状は、日常生活の質を大きく下げるものです。恥ずかしさから相談しにくいと感じる方もいらっしゃいますが、実は多くの方が同じようなお悩みを抱えています。
腸内環境の乱れや食生活の影響、過敏性腸症候群(IBS)などが原因となっているケースもあり、適切な対応で症状が軽減することも少なくありません。
大阪谷町よりおか内科・内視鏡クリニックでは、腸の不調やガスによるお腹の張り、便通に関するご相談にも丁寧に対応しています。検査や生活改善のアドバイスなども含め、患者様一人ひとりに合わせたサポートを行っておりますので、「これくらいの症状で受診していいのかな…」と悩まず、ぜひお気軽にご相談ください。