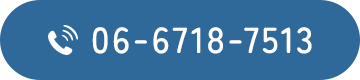- 胃や十二指腸の粘膜が傷つく「潰瘍」とは
- 胃潰瘍と十二指腸潰瘍の違いとは?
- ピロリ菌と薬が2大要因?主な原因
- 胃・十二指腸潰瘍の初期症状
- 胃・十二指腸潰瘍の検査・診断
- 胃・十二指腸潰瘍の治療
- 胃・十二指腸潰瘍の再発予防対策と注意点
- 胃・十二指腸潰瘍の食事について
胃や十二指腸の粘膜が傷つく「潰瘍」とは
 皮膚や粘膜などで、その組織が深く欠損してしまうことを「潰瘍」と言います。
皮膚や粘膜などで、その組織が深く欠損してしまうことを「潰瘍」と言います。
胃・十二指腸潰瘍では、胃や十二指腸の粘膜で、この潰瘍が生じます。胃酸・消化酵素が過剰に分泌されることなどが直接の原因となります。
胃・十二指腸潰瘍の根本的な原因としては、ピロリ菌感染、非ステロイド性抗炎症薬の内服などが挙げられます。近年は、ピロリ菌検査・除菌治療の普及によって胃・十二指腸潰瘍患者の総数は減少傾向にありますが、うち薬剤性の症例の割合は増加傾向にあります。
症状としては、上腹部・みぞおちの鈍い痛み、吐き気、胸やけなどが挙げられます。悪化し潰瘍から出血した場合には、吐血・黒色便なども見られます。また胃・十二指腸の壁に穴があくと激痛を伴う腹膜炎を合併します。重症例では命を落としてしまうことがある、決して侮ってはいけない病気です。
胃潰瘍と十二指腸潰瘍の違いとは?
胃潰瘍の特徴
- 胃の中で胃酸が粘膜を攻撃し、深い傷ができた状態です。
- 40代以上の中高年に多い傾向があります。
- 胃の働きが弱っているときに起こりやすく、食後に胃が重たい・キリキリ痛むなどの症状が出ることが多いです。
- 出血すると黒い便(タール便)が出ることもあります。
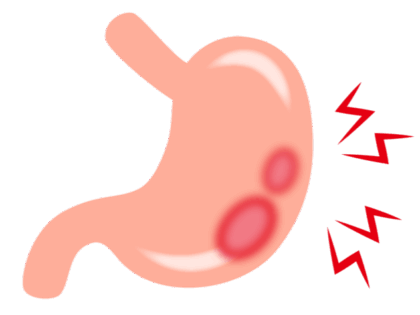
十二指腸潰瘍の特徴
- 胃のすぐ下にある「十二指腸」の粘膜が傷ついて起こります。
- 比較的若い世代にも多く見られるのが特徴です。
- 胃酸の分泌が多いタイプの方に起こりやすく、空腹時や夜間にお腹が痛むことが多く、食事をすると症状が軽くなる傾向があります。
- 潰瘍が深くなると出血や穿孔(穴があく)を起こすこともあります。
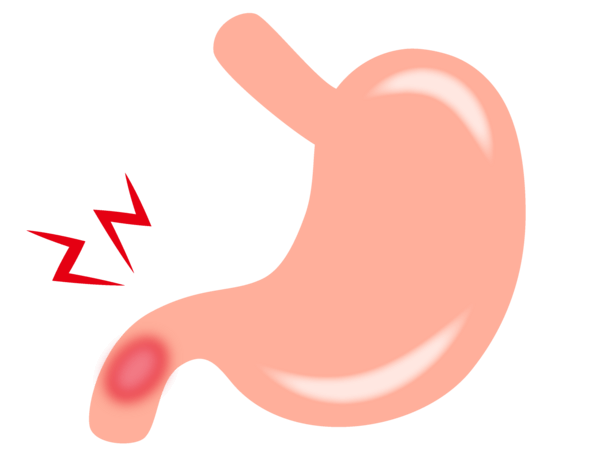
胃潰瘍と十二指腸潰瘍の比較表
| 比較項目 | 胃潰瘍 | 十二指腸潰瘍 |
|---|---|---|
| 発症部位 | 胃の中 | 胃の出口〜小腸の最初(十二指腸) |
| 好発年齢 | 中高年に多い | 若年層〜中年層にも多い |
| 痛みのタイミング | 食後の痛みが多い | 空腹時・夜間の痛みが多い |
| ピロリ菌との関連 | 強い | 非常に強い |
| 出血・穿孔リスク | あり | あり |
ピロリ菌と薬が2大要因?主な原因
胃・十二指腸潰瘍の2大要因として、ピロリ菌感染と非ステロイド性抗炎症薬の内服が挙げられます。また、喫煙やストレスが原因になることもあります。
ピロリ菌感染
ピロリ菌感染に伴う胃炎により、胃粘液の分泌が低下するために、潰瘍へと進展しやすくなります。
胃潰瘍の約7割、十二指腸潰瘍の約9割が、ピロリ菌感染を原因として発症すると言われています。ただし近年は、ピロリ菌検査・除菌治療の普及によって、ピロリ菌感染が原因となるケースは減少傾向にあります。
非ステロイド性抗炎症薬の内服
解熱・鎮痛・炎症抑制などを目的として使用される身近なお薬である非ステロイド性抗炎症薬は、胃粘膜を保護するプロスタグランジンの働きを抑える作用があります。そのため、その内服によって胃粘膜を守る機能が低下し、胃・十二指腸潰瘍の原因になることがあります。
なお、脳卒中や心筋梗塞の発症・再発予防として使用されるアスピリンも、非ステロイド性抗炎症薬の一種であり、同様に胃・十二指腸潰瘍の原因となることがあります。
喫煙
喫煙は、胃粘膜の血流を低下させて防御機能を弱めるとともに、胃酸やペプシンの分泌を促進することで攻撃因子を増やし、胃や十二指腸の粘膜を傷つけやすくします。また、ヘリコバクター・ピロリ菌の除菌治療の効果を下げることも知られており、特に十二指腸潰瘍とは強い関連があるとされています。
ストレス
ストレスも胃潰瘍や十二指腸潰瘍の発症や悪化に関与すると考えられています。精神的ストレスや外科的ストレス(手術や重い病気など)は、胃酸の分泌を促進したり、胃粘膜の血流を低下させたりすることで、粘膜の防御機能を弱め、潰瘍の原因となることがあります。
胃・十二指腸潰瘍の初期症状
胃潰瘍や十二指腸潰瘍の初期には、みぞおちの痛みや不快感、胸やけ、食欲不振などの症状が見られることがあります。特に十二指腸潰瘍では、空腹時や夜間に痛みが出て、食事で一時的に和らぐのが特徴です。
ただし、症状がはっきりしないことも多く、気づかないうちに進行している場合もあります。
受診すべき症状チェック
以下の症状がある方は、胃潰瘍・十二指腸潰瘍の可能性があります。
早めの受診・検査をおすすめします。
- 空腹時にみぞおちがキリキリ痛む
- 食後に胃が重たい・痛みが出る
- 胸やけや胃もたれが続いている
- 夜間や明け方にお腹が痛くなって目が覚める
- 胃の不快感が数週間以上続いている
- 吐き気や食欲不振がある
- 黒っぽい便(タール便)が出たことがある
- 吐血(血を吐いた)経験がある
- 市販の胃薬を飲んでも改善しない
- 痛み止め(NSAIDs)を長期で服用している
- ピロリ菌感染歴がある、または指摘されたことがある
- 家族に胃潰瘍・十二指腸潰瘍・胃がんの人がいる
胃・十二指腸潰瘍の検査・診断
 症状、服薬状況などから胃・十二指腸潰瘍が疑われる場合には、胃カメラ検査を行い、診断します。胃カメラ検査では、潰瘍の部位や形状、進行度を正確に把握し、治療方針の立案に活かすことができます。
症状、服薬状況などから胃・十二指腸潰瘍が疑われる場合には、胃カメラ検査を行い、診断します。胃カメラ検査では、潰瘍の部位や形状、進行度を正確に把握し、治療方針の立案に活かすことができます。
胃潰瘍は、胃がんとの鑑別が難しいこともあり、その場合には組織を採取して、顕微鏡を用いて病理検査を行い、良性か悪性(がん)かを判断し、確定診断とします。
穿孔が疑われる場合には、胃カメラ検査ではなく、先にCT検査が必要になることがあります。
胃・十二指腸潰瘍の治療
薬物療法
胃・十二指腸潰瘍の基本となる治療です。胃酸の分泌を抑える薬、胃粘膜の防御機能を高める薬などを使用します。多くの場合、薬物療法開始後6~8週間で潰瘍が治癒します。
また、非ステロイド性抗炎症薬やアスピリンなどを服用している場合には、休薬、お薬の変更などを検討します。
生活習慣指導
早期治癒のため、薬物療法と並行して進める必要があるのが、生活習慣指導です。
暴飲暴食、刺激物の摂り過ぎ、喫煙、飲酒を控えましょう。ストレスも極力、取り除きます。
除菌治療
胃カメラ検査の際には、組織を採取してピロリ菌検査を行うことが可能です。
その結果が陽性であった場合には、除菌治療は必須となります。ピロリ菌の感染を放置していると、胃・十二指腸潰瘍だけでなく、急性胃炎・慢性胃炎・萎縮性胃炎・胃がんなどのリスクが高まります。
内視鏡的治療・手術
潰瘍からの出血によって吐血が見られる場合には、内視鏡(胃カメラ)で止血処置を行います。
胃や十二指腸の壁に穴があく穿孔に至っている場合には、手術が必要になることが多くなります。
胃・十二指腸潰瘍の再発予防対策と注意点
処方されたお薬を正しく飲むこと
潰瘍が治癒するまでには、通常6~8週間ほどかかります。たとえ自覚症状が消失したとしても、医師の指示に従い、処方されたお薬の内服は継続してください。
薬物療法と並行して生活習慣の改善にも取り組むこと
早期治癒のため、暴飲暴食、刺激物の摂り過ぎ、喫煙、飲酒などを控えましょう。また治癒後も再発防止のため、できる限り習慣化した食生活を継続しましょう。
合併症が疑われる症状が出た時にはすぐに受診する
吐血、黒色便、めまい、動悸、激しい腹痛など、潰瘍からの多量出血・穿孔・腹膜炎といった合併症が疑われる症状があった時には、緊急入院や手術が必要になります。場合によっては命にかかわりますので、昼夜問わず、一刻も早く受診をしてください。
再発予防に取り組む
再発予防においては、改善した生活習慣をできるだけ維持すること、ピロリ菌検査で陽性だった場合には除菌治療を受けることなどが重要となります。
非ステロイド性抗炎症薬については休薬や薬の変更(COX-2選択的阻害薬などへの変更)を検討しますが、非ステロイド性抗炎症薬の内服を継続する必要がある場合には、胃酸を分泌する薬(プロトンポンプ阻害薬)、胃粘膜を保護する薬(プロスタグランジン製剤)を併用することで、潰瘍の再発を予防します。
非ステロイド性抗炎症薬の1種であるアスピリンの内服を継続する必要がある場合も、プロトンポンプ阻害薬・プロスタグランジン製剤の併用が、潰瘍の再発予防において有効となります。
胃・十二指腸潰瘍の食事について
胃や十二指腸に潰瘍ができているときは、刺激を避け、胃にやさしい食事を心がけることが大切です。
薬による治療とあわせて、毎日の食事を見直すことで、潰瘍の治りを早め、再発の予防にもつながります。
避けたほうがよい食べ物・飲み物
以下のようなものは、胃酸を刺激したり、粘膜を傷つけたりする可能性があるため、控えましょう。
- 香辛料(唐辛子、カレー粉、こしょう など)
- 油っこい料理(揚げ物、天ぷら、ラーメンなど)
- アルコール類(ビール、日本酒、ワイン など)
- コーヒー、濃い紅茶、炭酸飲料
- 酸味の強い果物(柑橘類、梅干しなど)
- 塩辛い・濃い味付けの食品(漬物、干物、加工食品など)
- 熱すぎる・冷たすぎる飲食物
潰瘍があるときにおすすめの食べ物
胃にやさしく、消化のよいものを選びましょう。
- 白がゆ・柔らかめのご飯
- うどん・そうめんなどのやわらかい麺類
- 白身魚、鶏のささみ(蒸す・ゆでる)
- 卵(半熟・茶わん蒸し・卵とじ)
- 野菜の煮物(よく火を通して柔らかく)
- 豆腐・湯豆腐・豆乳
- 牛乳・ヨーグルト(刺激がなければ)
- バナナ、りんごのすりおろしなどの消化のよい果物
食事のとり方のポイント
食材の選び方だけでなく、「食べ方」も大切です。
- 1日3食を規則正しく(空腹時間が長いと胃酸が粘膜を傷つけます)
- よく噛んで、ゆっくり食べる
- 寝る直前の食事は避ける(2~3時間は空ける)
- 暴飲暴食は避け、腹八分目を意識
- 熱すぎる・冷たすぎる飲食は避ける