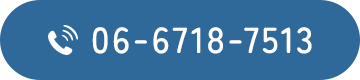消化器内科について
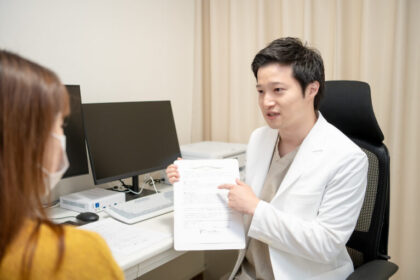 消化器内科では、食道、胃・十二指腸、小腸、大腸、肝臓、膵臓、胆嚢といった消化器の症状や疾患を診療します。
消化器内科では、食道、胃・十二指腸、小腸、大腸、肝臓、膵臓、胆嚢といった消化器の症状や疾患を診療します。
問診・診察の上、必要に応じて血液検査、腹部エコー検査、胃カメラ検査・大腸カメラ検査、CT検査などを行い、病気の早期発見と早期治療に努めます。
当院院長は、日本消化器病学会・日本消化器内視鏡学会・日本肝臓学会の専門医の資格を取得しております。豊富な経験と知識をもとに、正確な診断・治療を行います。胃カメラ検査・大腸カメラ検査においても、苦痛を抑えた精度の高い検査を行いますので、どうぞ安心してご相談ください。
当院で対応する消化器症状
消化器内科では、さまざまな内科的な症状を診療します。
- のどの違和感、飲み込みづらさ、声がれ
- 胸やけ
- 吐き気、嘔吐
- 吐血
- ストレスで胃痛と吐き気がする
- 胃痛、胃もたれ
- ゲップ、呑酸
- 早期飽満感(すぐに満腹を感じ、必要な量を食べられない)
- 食欲不振
- 食欲はあるけど胃が痛い
- 胃が臭い・胃からくる口臭を感じる
- 空腹時に気持ち悪くなる
- 健康診断で貧血と言われた
- 下痢と便秘を繰り返す
- おならが止まらない・ガスが溜まる
- 便の色がいつもと違う
- 急に体重が減ってきた
- バリウム検査で異常を指摘された
- 原因不明の背中や腰、肩の痛み
- 腹痛、お腹の張り
- 便秘、下痢
- 血便、粘液便
- 便潜血検査で一度でも陽性だった
- 便が細くなった
- 便がコロコロとしている
当院で対応する消化器疾患
食道の病気
食道裂孔ヘルニア
胸腔と腹腔を隔てる横隔膜には、食道が通るための穴があり、これを食道裂孔と言います。食道裂孔ヘルニアは、胃の上部が横隔膜を超え、胸腔側へと飛び出した状態を指します。加齢や腹圧の上昇を原因とし、胃酸が逆流しやすくなることから、逆流性食道炎の発症リスクが高まります。
逆流性食道炎
加齢に伴う下部食道括約筋の緩み、肥満に伴う腹圧の上昇などによって、胃酸が食道へと繰り返し逆流し、その粘膜を傷つける病気です。のどの違和感、飲み込みづらさ、ゲップ・呑酸、胸やけなどの症状を伴います。放置していると、バレット食道を起こしやすくなります。
バレット食道
主に逆流性食道炎を原因とし、食道粘膜が、胃の粘膜のように変性した状態を指します。この変性した粘膜をバレット上皮と言い、放置し拡大すると食道がんのリスクが高まります。バレット食道そのものは基本的に無症状ですが、原因となる逆流性食道炎の症状が見られます。
食道がん
喫煙・飲酒を主な原因として発症します。特に、60代以上で発症リスクが高まります。飲み込みづらさ、胸痛などの症状は、ある程度進行してから現れるケースが多くなります。一方で転移・進行しやすいがんであるため、リスクの高い人は定期的な胃カメラ検査をおすすめします。
胃の病気
慢性胃炎・萎縮性胃炎
ピロリ菌感染を放置していると、胃炎が慢性化した慢性胃炎を発症し、胃もたれ、胃の痛み、吐き気などの症状が現れます。放置していると胃の粘膜が薄くなる萎縮性胃炎へと進行し、胃がんのリスクが高くなります。
胃がん
ピロリ菌感染の放置、塩分の摂り過ぎ、喫煙などを原因とします。初期はほぼ無症状ですが、進行すると胃痛や胃もたれなどの症状が現れるようになります。早期発見のためには、定期的な胃カメラ検査が重要です。
機能性ディスペプシア
胃痛や胃もたれといった不快な症状が続いているのに、検査を行っても器質的な異常が認められない病気です。発症にはストレスが関与しているものと思われます。以前は「ストレス性胃炎」と呼ばれていました。
ピロリ菌感染
ピロリ菌は、小児期の親からの食事の口移し等で感染するものと考えられています。急性胃炎や慢性胃炎、胃・十二指腸潰瘍、胃がんの原因やリスク因子となるため、感染が認められた場合には除菌治療をおすすめします。
胃アニサキス症
魚介類を食べることでアニサキスが胃に感染した状態です。主な症状は腹痛です。胃カメラ検査によって摘出すれば、症状は速やかに軽快します。摘出が困難である場合も、お薬で軽快させることができます。
腸の病気
十二指腸潰瘍
ピロリ菌感染、痛み止めの内服などを原因として、十二指腸の粘膜がえぐれる病気です。みぞおち・背中の痛み、吐き気といった症状を伴います。重症例では、吐血に至ることもあります。
急性腸炎
細菌やウイルスの感染、アレルギーなどを原因として起こる腸炎です。腹痛や吐き気・嘔吐、下痢、発熱などの症状を伴います。細菌性の場合は、血便が出ることもあります。ご家族への感染を防ぐためにも、お早目にご相談ください。
大腸ポリープ
大腸粘膜に生じるポリープです。一部は、放置していると大きくなり、がん化します。そのため、がん化のおそれのある大腸ポリープはできる限りの切除が推奨されます。当院でも対応しております。
大腸がん
食生活の欧米化、運動不足、肥満、飲酒・喫煙などを原因とします。初期であれば内視鏡による治療が可能です。症状としては、血便、便秘・下痢、便が細くなる、残便感、腹痛・お腹の張りなどが挙げられます。早期発見のため、定期的に大腸カメラ検査を受けましょう。
大腸憩室症
腹圧の上昇などを原因として、大腸壁の一部が、外側に向けて突出した状態です。基本的に無症状ですが、憩室内で炎症が起こり、腹痛、便秘、下痢、血便、発熱などの症状が見られることがあります(大腸憩室炎)。
過敏性腸症候群
大腸カメラ検査で異常が見つからないのに、慢性的な便秘・下痢・腹痛といった症状が続く病気です。過度のストレス、自律神経の乱れが発症に影響すると考えられています。大腸カメラ検査で他の病気を除外した上で正確に診断し、治療することが大切です。
潰瘍性大腸炎
クローン病と共に炎症性腸疾患に分類され、難病の指定を受けている病気です。大腸粘膜に炎症が生じ、腹痛・下痢・血便といった症状が見られます。適切な治療によって症状が抑えられる寛解期を維持することで、以前と変わらない生活を送ることが可能です。
クローン病
小腸や大腸を中心に、消化管で連続した炎症が認められる病気です。潰瘍性大腸炎との違いは、口~肛門まで、すべての消化管で炎症が起こり得る点です。主な症状に、下痢・腹痛、血便、体重減少が挙げられます。適切な治療により、症状をコントロールします。
虚血性大腸炎
動脈硬化、慢性的な便秘などを原因として、大腸の血流が悪くなる病気です。大腸粘膜に炎症や潰瘍が生じ、腹痛・血便などの症状が見られます。60歳以上の便秘気味の女性に多い病気ですが、近年では若い世代でも発症数が増加しています。
腸閉塞
さまざまな原因によって、腸で内容物が詰まってしまった状態です。吐き気・嘔吐、腹痛などの症状を伴います。内視鏡的治療・手術が必要になることもあります。
当院が行う検査
大腸カメラ検査
(下部消化管内視鏡検査)
肛門から内視鏡を挿入し、大腸粘膜を観察します。炎症や潰瘍・がんなどを早期発見することが可能です。また大腸ポリープの切除、初期大腸がんの治療なども可能です。
CT検査
X線を身体のまわりから当て、透過したX線量をコンピュータ処理することで、身体を輪切りした画像を取得できる検査です。二次元の画像を取得する一般的なレントゲン検査よりも、詳細な情報が得られます。当院では、16列マルチスライスCTを導入しておりますので、短時間・低被ばくでの撮影が可能です。
腹部超音波検査
身体の表面から超音波を当て、内臓や血管の状態を調べることができます。対象となる内臓には、肝臓、胆のう、膵臓、腎臓などが挙げられます。レントゲン検査やCT検査と異なり被ばくがなく、また痛みもないため、妊娠中の女性やお子様を含めてどなたでも安心して受けられます。ただし、検査前は絶食が必要です。また胃の空気・皮下脂肪が多い場合には観察が難しくなることがあります。
血液検査・尿検査
血液検査では、貧血・炎症の有無、肝機能、腫瘍マーカーなどを調べられます。
尿検査では、膀胱炎、尿路結石などが診断できます。
肛門診療について
 当院では、胃や腸といった消化器だけでなく、肛門に関わる病気や症状の診療も行っております。
当院では、胃や腸といった消化器だけでなく、肛門に関わる病気や症状の診療も行っております。
肛門の不調は「恥ずかしい」「受診しづらい」と感じる患者様も多いですが、痔(いぼ痔・切れ痔・痔ろう)をはじめとする肛門の病気は、日常生活に支障をきたしたり、大腸がんなど重大な病気が隠れている場合もあります。気になる症状がある方は、どうぞお気軽にご相談ください。
幅広い診療科があるため受診理由が目立ちません
内科・消化器内科・肝臓内科などの診療も行っておりますので、「肛門のことで来た」と周囲に気付かれる心配が少なく、安心して受診いただけます。
プライバシーに配慮した個室診察
診察は個室で行い、患者様のプライバシーに十分配慮しております。恥ずかしさを感じることなく安心してご相談いただけます。
専門性の高い診断・治療
日本消化器内視鏡学会専門医による診断・治療を行います。必要に応じて大腸カメラ検査で腸全体を確認し、より正確に原因を突き止めます。
必要に応じて専門機関へ紹介
外科的治療が必要な場合には、速やかに連携病院をご紹介いたします。初期段階から重症例まで、適切な医療へとつなげることが可能です。
当院で対応する肛門の症状
当院では、さまざまな肛門の症状を診療します。
- 肛門の痛み・かゆみ
- 出血(トイレットペーパーに血がつく、便に血が混じる など)
- 肛門の腫れやしこり
- 排便時の強い痛み
- 膿や分泌物が出る
- 便が漏れる・間に合わない
当院で対応する肛門疾患
痔核(いぼ痔)
肛門の血管がうっ血して腫れることで発症します。排便時の出血や肛門の腫れ、違和感を伴うのが特徴です。
進行すると肛門の外に痔が出てきて戻らなくなることもあります。生活習慣の改善や内服・外用薬でコントロールできる場合もありますが、重症例では外科的治療が必要です。
裂肛(切れ痔)
硬い便や下痢などによって肛門の皮膚が裂け、排便時に強い痛みと鮮血が出ます。痛みのため排便を避けるようになり、便秘が悪化してさらに症状を繰り返す悪循環に陥ることもあります。
慢性化すると肛門の狭窄を引き起こし、手術が必要になることもあります。
痔ろう
肛門周囲にたまった膿が皮膚に通じる管(トンネル)をつくった状態です。
膿が出続けたり、炎症を繰り返すのが特徴で、自然に治ることはありません。根治には外科的治療が必要となりますが、早期の発見・治療で再発のリスクを減らすことができます。
肛門周囲膿瘍
細菌感染によって肛門周囲に膿がたまり、腫れや激しい痛み、発熱を伴います。
放置すると痔ろうに進展することが多いため、早期に切開・排膿などの処置が必要です。強い痛みを感じる場合は、すぐにご相談ください。
直腸脱・肛門機能障害
肛門や直腸が外に飛び出す直腸脱、または便が漏れてしまう肛門機能障害は、加齢や出産後、骨盤底筋のゆるみなどを原因に発症します。
生活の質に大きく影響しますが、リハビリや薬物療法、必要に応じて外科的治療で改善を図ることが可能です。
当院が行う検査
視診・触診
肛門の外側の状態を観察し、腫れ・裂け目・しこりなどを確認します。必要に応じて指診を行い、内部の異常やしこりの有無を調べます。
肛門鏡検査
-
小型の器具を用いて肛門内部を観察します。痔核・裂肛の有無や出血の部位などを確認できます。
大腸カメラ検査(下部消化管内視鏡検査)
肛門症状が大腸の病気によって起きている可能性もあるため、必要に応じて大腸全体を観察します。大腸ポリープや大腸がん、炎症性腸疾患などの発見にも有効です。
血液検査
貧血や炎症の有無、感染の可能性などを調べます。出血が続いている場合や膿が出ている場合に重要です。