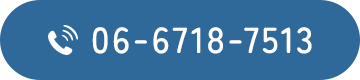- すぐに疲れる・寝ても疲れが取れないと感じていませんか?
- 疲れやすい・だるさが続く原因は?
- 疲れやすい・だるさを感じる病気
- すぐに疲れる・寝ても疲れが取れない時の対処法
- 疲れやすさに対して内科で行う検査
- 寝ても疲れが取れない…そんなときは専門医にご相談を
すぐに疲れる・寝ても疲れが取れないと感じていませんか?
 「最近すぐ疲れる…」「たっぷり寝たはずなのに朝からだるい」
「最近すぐ疲れる…」「たっぷり寝たはずなのに朝からだるい」
そんなお悩みを、年齢や忙しさのせいにしていませんか?
もちろん、ストレスや睡眠不足、過労によって一時的に疲れがたまることはあります。
しかし、いつまでも疲労感が抜けない、だるさが慢性的に続く場合は、体の不調や病気のサインかもしれません。
特に、貧血や甲状腺の異常、糖尿病、睡眠時無呼吸症候群、肝臓・腎臓機能の低下など、内科的な疾患が隠れているケースも少なくありません。
「休めば治るだろう」と我慢せず、一度内科での検査を受けてみることが、将来の健康を守る第一歩になります。
疲れやすい・だるさが続く原因は?
疲れやすさやだるさが続く原因には、以下のようなものがあります。
加齢
年齢を重ねると、体内で活性酸素が増え、神経細胞が破壊されることで、疲れやすさ・だるさを感じることがあります。また運動量が少ない人は、筋力・体力の低下により、以前と同じ活動量でも疲れやだるさを感じやすくなります。
睡眠不足・不規則な生活
仕事や家事で忙しく睡眠不足になったり、生活リズムが不規則になると、心身の疲れを十分に取ることができません。自律神経の乱れにもつながり、疲れやすさ・だるさ以外にも、さまざまな体調不良が起こりやすくなります。
ストレス
強いストレスは、睡眠不足や不規則な生活と同様に、自律神経のバランスを乱します。またストレスから眠れない、暴飲暴食に走るといったケースも多く、それがより疲れやすさやだるさといった体調不良に拍車をかけます。
暴飲暴食
健康を維持するためには、栄養バランスの整った食事が不可欠です。反対に、栄養が偏ったり、食べ過ぎたりしてしまうと、疲れやすさやだるさなどの原因となります。
ホルモンバランスの乱れ
女性の場合、月経や妊娠・出産の際、あるいは更年期などに、ホルモンバランスが大きく変動します。これにより、疲れやすさやだるさの症状が続くことがあります。近年は、月経前症候群でお悩みの方も増えています。
貧血
貧血とは、赤血球に含まれるヘモグロビンの量が不足している状態を指します。全身への酸素供給能力が低下することで、疲れやすさやだるさ、動悸、息切れ、めまいなどの症状が引き起こされます。
疲れやすい・だるさを感じる病気
糖尿病
糖尿病になると、インスリンの不足・働きの低下によって、血中のブドウ糖をうまく細胞に取り込めなくなります。これにより、エネルギー代謝のバランスが崩れ、疲れやすさ・だるさなどの症状が引き起こされます。その他、のどの異常な渇き、多尿・頻尿、体重減少などの症状も見られます。
睡眠時無呼吸症候群(SAS)
睡眠中に繰り返し無呼吸・低呼吸が起こる病気です。多くは、いびきを伴います。眠りが浅くなることから、日中に眠気や疲れ、だるさを感じます。無呼吸時には全身が酸素不足に陥るため、心筋梗塞など重大な病気のリスクも高まります。当院では、睡眠時無呼吸症候群の専門外来を開設しています。
肝障害・腎臓病
脂肪肝、ウイルス性肝炎、腎臓病の症状として、疲労感やだるさが見られることがあります。ただ、いずれも初期には自覚症状が乏しいため、健康診断などで異常を指摘され、発見につながることが多くなります。異常を指摘された場合には、必ず再検査や精密検査を受けましょう。
甲状腺機能低下症
甲状腺ホルモンの分泌が不足する病気です。新陳代謝が低下することで、疲労感・倦怠感、寒気、むくみ、気分の落ち込み、皮膚の乾燥などの症状が引き起こされます。特に女性に多く見られますが、「年齢のせいだろう」と受診に至らないケースが少なくありません。
感染症
ウイルスや細菌などの感染によって、その症状として疲れやすさ・だるさを感じることがあります。風邪やインフルエンザがその代表です。
自律神経失調症
過度のストレスによって、自律神経のバランスが崩れ、さまざまな症状が現れます。具体的には、動悸、ふらつき、多汗、高血圧、下痢・便秘、頭痛、肩こり、倦怠感、疲労感などが挙げられます。同じくストレスを原因とするうつ病に合併することもあります。
うつ病
著しい気分の落ち込みが続く病気です。仕事や勉強はおろか、日常生活中のちょっとした作業や動作(洗顔・入浴・食事など)でも疲れやだるさを感じ、またそれらに対する意欲や関心も薄れます。不眠/過眠、集中力低下、自責の念などが見られることもあります。
すぐに疲れる・寝ても疲れが取れない時の対処法
十分な睡眠・規則正しい生活を取り戻す
質・量ともに十分な睡眠をとること、規則正しい生活を送ることで、自律神経が整い、症状の改善が期待できます。
ストレスの解消
ストレスの原因を取り除ければ理想的ですが、ストレスをうまく解消することも大切です。スポーツや旅行、趣味など、自分に合ったストレス解消法を見つけ、実践していきましょう。
適度な運動
過度な運動不足は、血流や筋力・体力の低下を招きます。激しいものでなくて構いませんので、ウォーキング(散歩)、家事、朝の体操、お風呂あがりのストレッチなど、適度な運動を継続していきましょう。
食習慣の見直し
栄養の偏りや不足、食べ過ぎ・お酒の飲み過ぎなどがある場合には、改善しましょう。疲労回復に役立つビタミンB群、貧血の改善・予防のための鉄などを、意識して摂ることをおすすめします。
疲れやすさに対して内科で行う検査
血液検査
疲労の原因となるさまざまな内科的疾患を調べるために、まず血液検査を行います。
調べる項目の例
貧血(赤血球・ヘモグロビン・フェリチン)
肝機能(AST・ALT・γ-GTP・ALPなど)
腎機能(クレアチニン・BUNなど)
血糖値・HbA1c(糖尿病の有無)
甲状腺ホルモン(TSH・FT3・FT4)
炎症反応(CRP)やビタミン・ミネラル不足のチェック
睡眠時無呼吸症候群の簡易検査
睡眠の質が悪く、日中に強い眠気や集中力の低下がある方には、自宅で行えるスクリーニング検査を実施します。
睡眠中に呼吸が止まっているかどうかを確認することで、見過ごされやすい睡眠の質の低下による疲労を評価できます。
画像検査(超音波・CT)
慢性的なだるさの背景に内臓の異常や腫瘍、脂肪肝、副腎疾患などが隠れていることもあります。
当院では、腹部エコー(超音波)による負担の少ない検査に加えて、クリニックではめずらしい64列のCTを導入しており、肝臓・腎臓・膵臓・副腎などの状態を詳細に確認することが可能です。
心電図やホルター心電図(必要時)
動悸や息切れ、胸の不快感などが伴う場合は、心臓の異常がないかを評価するための心電図検査を行うこともあります。
寝ても疲れが取れない…そんなときは専門医にご相談を
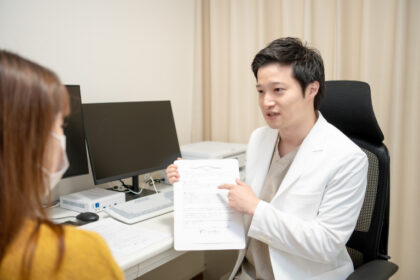 「すぐに疲れる」「寝ても疲れが取れない」といった症状は、日常生活の中で起こりやすいものですが、内科的な病気が隠れていることも少なくありません。
「すぐに疲れる」「寝ても疲れが取れない」といった症状は、日常生活の中で起こりやすいものですが、内科的な病気が隠れていることも少なくありません。
当院では、複数の専門医資格をもつ医師が、肝臓や甲状腺、糖尿病などの内科疾患を含め、疲労の原因を丁寧に調べ、必要に応じた検査や生活改善のアドバイスを行っています。
なんとなく不調が続く…という段階でも、気軽にご相談いただけるクリニックを目指しています。
症状が続く方は、お一人で抱え込まず、まずはお気軽にご来院ください。