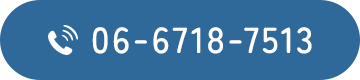- 肝臓内科について
- 当院の肝臓内科の特徴
- このような症状・健診結果がある方へ
- 当院で対応する肝臓内科の病気
- 当院で行う肝臓内科の検査
- 肝機能を改善・回復するには
- 肝機能異常を放置せず、早期の受診・治療を
肝臓内科について
 当院では、日本肝臓学会・肝臓専門医である院長が、肝臓疾患の診断・治療を行います。
当院では、日本肝臓学会・肝臓専門医である院長が、肝臓疾患の診断・治療を行います。
肝臓は、沈黙の臓器と呼ばれるほど、障害されても自覚症状の出にくい内臓です。また、現れる症状も全身倦怠感、食欲不振など、受診と結びつきにくいものが少なくありません。肝障害を長く放置していると、肝硬変や肝がんなど重大な病気を合併するリスクも高まります。
なんとなく体調が良くないという状態が続く場合、また健康診断などで肝臓の数値の異常を指摘された場合には、お早目に当院の肝臓内科にご相談ください。
当院の肝臓内科の特徴
肝臓専門医による的確な診断と全身管理
 当院の院長は、日本肝臓学会認定 肝臓専門医として、脂肪肝やNASH、ウイルス性肝炎、肝機能障害など、幅広い肝疾患に対応しています。さらに、消化器病専門医・内視鏡専門医・総合内科専門医としての視点も持ち合わせており、肝臓だけでなく全身の状態を踏まえた診療が可能です。
当院の院長は、日本肝臓学会認定 肝臓専門医として、脂肪肝やNASH、ウイルス性肝炎、肝機能障害など、幅広い肝疾患に対応しています。さらに、消化器病専門医・内視鏡専門医・総合内科専門医としての視点も持ち合わせており、肝臓だけでなく全身の状態を踏まえた診療が可能です。
消化器・内科を横断して診られる強み
 肝臓病は糖尿病や高脂血症、高血圧、肥満などの生活習慣病と深く関わっています。当院では、消化器内科・肝臓内科・内科疾患を横断的に診療できる体制が整っており、原因の特定から再発予防まで一貫したサポートが可能です。生活指導や栄養管理も含めて、患者様の体質や生活習慣に合った改善を目指します。
肝臓病は糖尿病や高脂血症、高血圧、肥満などの生活習慣病と深く関わっています。当院では、消化器内科・肝臓内科・内科疾患を横断的に診療できる体制が整っており、原因の特定から再発予防まで一貫したサポートが可能です。生活指導や栄養管理も含めて、患者様の体質や生活習慣に合った改善を目指します。
CT・腹部エコーなど検査設備が充実
 当院では、肝臓疾患の早期発見と正確な診断に必要な検査体制も整えています。肝機能異常を指摘された方には、腹部エコー検査や血液検査に加え、CTによる脂肪肝や肝腫瘍の評価などを組み合わせ、詳細に状態を把握します。健診で「AST・ALTが高い」「γ-GTPが高い」と言われた方も、適切な検査と治療方針をご案内します。
当院では、肝臓疾患の早期発見と正確な診断に必要な検査体制も整えています。肝機能異常を指摘された方には、腹部エコー検査や血液検査に加え、CTによる脂肪肝や肝腫瘍の評価などを組み合わせ、詳細に状態を把握します。健診で「AST・ALTが高い」「γ-GTPが高い」と言われた方も、適切な検査と治療方針をご案内します。
高度医療機関との連携による安心の診療体制
 必要に応じて、大阪公立大学医学部附属病院、大阪医療センター、大阪赤十字病院、大阪けいさつ病院、大阪国際がんセンターなど、地域の高度医療機関とスムーズに連携いたします。肝生検や入院加療、肝がん治療などが必要と判断された場合にも迅速に紹介いたしますので、安心してご相談ください。
必要に応じて、大阪公立大学医学部附属病院、大阪医療センター、大阪赤十字病院、大阪けいさつ病院、大阪国際がんセンターなど、地域の高度医療機関とスムーズに連携いたします。肝生検や入院加療、肝がん治療などが必要と判断された場合にも迅速に紹介いたしますので、安心してご相談ください。
このような症状・健診結果がある方へ
肝障害が進むと、以下のような症状が現れます。また健康診断などで異常を指摘された場合も、お早目にご相談ください。
- すぐに疲れる・寝ても疲れが取れない
- 食欲不振
- 黄疸(皮膚・白目が黄色くなる)
- お腹の張り
- 右脇腹が痛い・重い
- むくみが取れない
- かゆみが止まらない
- 尿の色が異様に濃い
- 健康診断などで肝機能(AST・ALT・γ-GTP)の数値の異常を指摘された
- お酒を飲まないのに肝臓の数値が高い
当院で対応する肝臓内科の病気
B型肝炎
B型肝炎ウイルスの感染を原因とします。母子感染、性交渉、輸血、刺青・タトゥー、臓器移植、針刺し事故などの感染経路が考えられます。
一過性の感染に終わることもありますが、6ヶ月以上感染が続くB型慢性肝炎の場合は、内服薬を用いて病気の悪化を防がなければなりません。
C型肝炎
C型肝炎ウイルスの感染を原因とします。性交渉、刺青・タトゥー、針刺し事故、長期の血液透析などの感染経路が考えられます。
C型肝炎は慢性化しやすく、肝硬変・肝がんを合併するリスクも高くなります。インターフェロンフリーの内服薬を用いて、ウイルスの排除を図ります。
脂肪肝
肝臓に脂肪が蓄積している状態です。原因としては、肥満や食べ過ぎ・飲み過ぎ、運動不足、糖尿病や脂質異常症などの生活習慣病が挙げられます。
脂肪肝の段階でしたら、食習慣・運動習慣の改善によって、肝臓を健康な状態へと戻すことが可能です。一方で放置していたり、数値が良くなったからといって生活習慣を元に戻してしまうと、進行し、肝硬変や肝がんの発症リスクが高まります。
非アルコール性脂肪性肝炎
お酒をまったく・ほとんど飲まない方に発症する脂肪性肝炎です。食べ過ぎ、運動不足などの生活習慣の乱れ、生活習慣病を主な原因とします。
放置していると、肝硬変・肝がんへと進行することがあります。治療では、食事療法・運動療法に加え、薬物療法を行います。
アルコール性肝障害
長期にわたる多量の飲酒を主な原因として発症する肝障害の総称です。脂肪肝や肝線維症などがこれに該当します。放置していると、肝硬変や肝がんへと進行するおそれがあります。
原発性胆汁性胆管炎
原発性胆汁性胆管炎は、自己免疫の異常により肝臓内の細かい胆管が徐々に壊れていく病気です。胆汁の流れが悪くなることで、肝臓にダメージが蓄積し、進行すると肝硬変に至ることがあります。早期発見と適切な内服治療が進行を遅らせる鍵となります。
自己免疫性肝疾患
免疫の異常によって肝臓が攻撃を受けて障害される病気の総称です。
肝細胞が障害される自己免疫性肝炎、胆管が障害される原発性胆汁性胆管炎や原発性硬化性胆管炎などがあります。原発性胆汁性胆管炎や原発性硬化性胆管炎では、胆汁によって肝細胞が破壊されてしまいます。
基本的に自覚症状はありませんが、倦怠感・黄疸を伴う急性肝炎として発症することもあります。
治療では、免疫を抑制する副腎皮質ステロイドの内服を行います。途中で治療を中断すると短期間で肝不全、肝硬変へと進行することがあるため注意が必要です。
肝硬変
慢性肝炎などによって障害され続けた肝臓が、線維化・硬化する病気です。具体的な原因疾患としては、B型肝炎、C型肝炎、脂肪肝、アルコール性肝障害、自己免疫肝疾患などが挙げられます。
初期の肝硬変にはほとんど自覚症状がありませんが、進行すると黄疸、むくみ、お腹の張り、腹水、尿量減少といった症状が現れることがあります。放置していると肝がんへと進行することがあるため、早期に治療を開始する必要があります。
肝癌
肝癌は、肝臓にできる悪性腫瘍で、日本ではB型・C型肝炎や肝硬変、脂肪肝などが原因となることが多い病気です。初期には自覚症状が乏しく、健康診断や定期的な画像検査で偶然見つかることもあります。
早期発見が治療成績を左右するため、定期検査が重要です。
胆石症
胆石症は、胆嚢や胆管に石(胆石)ができる病気です。食後に右上腹部の痛みや吐き気などを引き起こすことがあり、石が詰まると胆嚢炎や膵炎など重篤な合併症を招くこともあります。
症状がある場合は、胆嚢の摘出手術が検討されます。
胆嚢ポリープ
胆嚢ポリープは、胆嚢の内壁にできる隆起性の病変で、多くは良性です。小さなポリープは経過観察されることが多いですが、サイズが大きい場合や増大傾向がある場合には、悪性の可能性も考慮して手術を検討します。
定期的なエコー検査が重要です。
当院で行う肝臓内科の検査
肝臓疾患は自覚症状が出にくく、健診などで数値の異常を指摘されてはじめて気づくケースが少なくありません。当院では、異常の原因を正確に把握し、重症度や進行具合を評価するための検査を行っています。
血液検査(肝機能検査)
AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、ALP、LDH、総ビリルビンなどを測定し、肝細胞の障害や胆汁の流れの異常を確認します。脂肪肝やNASH、アルコール性肝障害、肝炎などのスクリーニングにも重要な検査です。
腹部超音波(エコー)検査
肝臓の大きさ・形・硬さ・脂肪の付き具合などをリアルタイムで確認できる負担の少ない検査です。脂肪肝、肝腫瘤(しこり)、肝硬変の進行具合の目安などを調べます。
腹部CT検査
より詳細な評価が必要な場合にはCT検査を行い、肝臓の構造や血管の状態、腫瘍の有無などを確認します。脂肪肝の重症度評価や、肝がんの精査・経過観察にも活用されます。
ウイルス検査
B型・C型肝炎ウイルスの感染の有無を調べる血液検査です。慢性肝炎や肝硬変、肝がんのリスク評価にも重要です。過去に感染歴がある方や、献血で指摘された方もご相談ください。
腫瘍マーカー検査
肝がんのスクリーニングとして、AFP、PIVKA-IIなどの腫瘍マーカーを必要に応じて測定します。特に肝硬変や慢性肝疾患がある方には定期的な検査が推奨されます。
肝機能を改善・回復するには
健診でAST(GOT)やALT(GPT)、γ-GTPなどの数値が高いと指摘された方は、肝臓に負担がかかっているサインかもしれません。肝機能の異常は、脂肪肝・アルコール性肝障害・薬剤性肝障害など、さまざまな原因が考えられますが、多くは生活習慣の改善によって回復が可能です。
食事の見直し
- 脂質や糖質の摂りすぎを控える
- 野菜・海藻・きのこなど食物繊維をしっかり摂る
- 肝臓に良いとされる食品(大豆製品、青魚、ビタミンB群、亜鉛など)を意識的に
- 過剰な塩分や加工食品の摂取も控えめに
アルコールの制限
- 毎日の飲酒は肝臓への負担になります
- 休肝日を設ける、または一定期間禁酒することで数値が改善することも
- 脂肪肝や肝機能障害が指摘された方は断酒をおすすめするケースもあります
適度な運動
- ウォーキングや軽い筋トレなど、週に150分程度の有酸素運動が推奨されます
- 内臓脂肪の減少やインスリン抵抗性の改善により、肝機能も改善されやすくなります
十分な睡眠とストレス管理
- 肝臓の再生は主に睡眠中に行われます。質の良い睡眠と規則正しい生活リズムが肝機能回復のカギとなります
- 過度なストレスは自律神経を乱し、代謝や肝臓の働きにも影響を与えることがあります
医師の指導のもとでの治療
- 数値が高いまま改善しない場合や、原因が明らかでない場合には肝臓専門医による評価と治療が必要です
- 薬剤性肝障害のリスクがある場合は、服用薬の見直しも行います
- 脂肪肝やNASHが疑われる場合には、CTや血液検査などによる評価を行い、生活指導と必要に応じて薬物療法を開始します
サプリメントに頼りすぎない
- 「肝臓に良い」とされるサプリも多くありますが、中には肝臓に負担をかける成分を含むものもあります
- 自己判断での使用は避け、必ず医師に相談のうえで活用してください
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれるほど、異常があっても自覚症状が出にくい臓器です。
健診で肝機能異常を指摘された方や、生活習慣に心当たりのある方は、早めに肝臓内科を受診し、状態を確認することが肝機能改善の第一歩です。
肝機能異常を放置せず、早期の受診・治療を
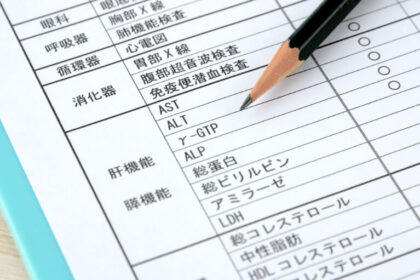 肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が出にくいまま病気が進行することが少なくありません。健康診断でAST・ALT・γ-GTPの異常を指摘された方や、倦怠感・食欲不振・体重減少などの気になる症状が続いている方は、肝臓疾患のサインかもしれません。
肝臓は「沈黙の臓器」と呼ばれ、症状が出にくいまま病気が進行することが少なくありません。健康診断でAST・ALT・γ-GTPの異常を指摘された方や、倦怠感・食欲不振・体重減少などの気になる症状が続いている方は、肝臓疾患のサインかもしれません。
当院では、日本肝臓学会認定の肝臓専門医が在籍し、CTやエコーなどの精密検査と全身を見据えた診療体制で、肝臓病の早期発見・治療に努めています。「数値が気になる」「体調に不安がある」と感じたら、どうぞお気軽に当院の肝臓内科にご相談ください。